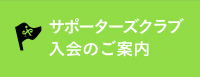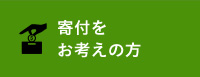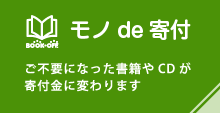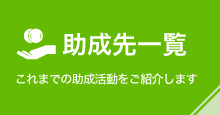【インタビュー】極東退屈道場 主宰:林慎一郎さん
2016年10月17日
林 慎一郎さん(極東退屈道場)インタビュー
今年アーツサポート関西は、演劇ユニット「極東退屈道場」を助成しています。伊丹アイホールで10月28日から始まる助成対象事業「百式サクセション」の稽古場にお邪魔して、主宰の林慎一郎さんにお話を聞いてきました。
――― 演劇をはじめるきっかけは?
林: 京都大学3回生の時、知り合いから誘われて劇団の立ち上げに参加したのがきっかけです。二回目の公演以降、たまたま僕が脚本を書くことになり、ついでに演出もする、という感じでした。その当時の京都には面白い演劇がいろいろあって、見てはいたのですが、やりたいと思ったことはなく、たまたま友人が誘ってくれたので参加してみたのがきっかけです。
 極東退屈道場 林 慎一郎さん
極東退屈道場 林 慎一郎さん――― そして「極東退屈道場」を2007年に立ち上げられました
林: メンバーが30歳代に入り考え方もいろいろ出てきたので、この最初の劇団は一旦解散となったのですが、僕自身は台本を書くことに興味が出てきた時期で、まず台本を書いて、その作品を上演するために俳優を集めるユニット形式で演劇を再開したのがこの「極東退屈道場」です。
―――― 「極東退屈道場」として目指しているスタイルのようなものはありますか
林: 「極東退屈道場」として書いた4作目に「サブウェイ」という戯曲があるのですが、思いがけずOMS戯曲賞をいただくこととなり、それをきっかけに自分のスタイルを自覚するようになりました。まず基本的に都市論なんですね。僕は北海道の函館出身で、大学で京都に来てそれから大阪に住み、都市の環境に住んで20年以上になります。たまに故郷に帰ると、故郷の喪失感や異邦人的な感覚を覚えます。そうしたことを手掛かりに都市の風景をいろんな視点で描こうとしています。
 極東退屈道場「サブウェイ」撮影:石川隆三
極東退屈道場「サブウェイ」撮影:石川隆三――― 今年6月に亡くなられた維新派の松本雄吉さんと、今年の2月、林さんが脚本を、そして演出を松本さんが担当されて豊中市の依嘱による演劇「PORTAL」が上演されました。そこでも都市の風景がテーマになっていたように思います
林: 維新派のヂャンヂャン☆オペラと呼ばれる変拍子のリズムの使い方などについて、松本さんと一緒に話し合いながら作った戯曲でした。演劇で地図を表現するアイデアを松本さんがとても面白いね、と。やはりここでも都市の風景を浮かび上がらせようとしました。
――― 林さんの演劇にはダンスの要素もありますよね
林: 4作目の「サブウェイ」あたりからなのですが、試行錯誤しながらやっています。まず脚本があって、それを見て振付家がダンスに落とし込んでいく共同演出的な手法をとっています。言葉をどのように身体化していくか。とてもスリリングな作業ですね。
 「PORTAL」撮影:井上嘉和
「PORTAL」撮影:井上嘉和――― 最近の演劇の傾向として、ダンスと演劇の境界があいまいになってきているように感じます。つまり、ダンサーが俳優として台詞を言う演技をし、俳優にダンサー的な身体性を求められるといった風に。そうしたものを意識されていますか。
林: ダンスによる身体を使った抽象的な表現の先に、さらに言葉による表現の広がりがあっても良い、という考え方は出てきているかもしれません。一方、僕は演劇において、舞台にゴロンと立つ俳優の身体の存在感そのものが俳優の特権みたいな考え方が根強くあって、演出家として言葉を語る俳優に厳しく身体性を求めるということはあまりせずにやってきたように思います。これからは、ダンス的な表現技術を持つ俳優による演劇の可能性が広がってきていても良いとは思いますね。
――― 今回の新作「百式サクセション」は、シェイクスピアのリア王をモチーフに、都市の中で老婆を探すストーリーとお聞きしています
林: 母である行方不明の老婆を都市の中で探すというのが、縦糸のような淡いストーリーとなっていて、青空カラオケに集うさまざまな人々が登場します。莫大な遺産を持つとうそぶくおばあちゃんが百円を握りしめて青空カラオケに興じるその周辺で、いろいろなエピソードが展開していきます。
――― 今回の新作について「報告劇」という言い方をされています。それはどのようなものなのでしょうか。
林: これまでも僕の演劇ではモノローグを良く使ってきたのですが、一般的にモノローグとは俳優が観客に向けて話しかけるものです。それに対して、僕の場合は、見えないインタビュアーに向けて状況をまさに「報告」する形をとっています。それを今回「報告劇」と呼ぶことにしました。今回の新作では、都市が、老いていく人々を見つめる眼差しを報告していく、という内容で、そうしたモノローグの断片を繋いでいくことによって、おぼろげな作品の輪郭が立ち上がってくるような作り方をしています。
 極東退屈道場「百式サクセション」稽古場風景
極東退屈道場「百式サクセション」稽古場風景――― 大阪の演劇を取り巻く状況を林さんはどう見ていらっしゃいますか
林: かつてあった例えば扇町ミュージアムスクエアのようなサロン的な劇場がなくなっています。演劇人が多く出入し情報収集や交換の場になるような場がありません。いくつかの民間劇場が頑張ってくれているのですが、なかなか大きな状況を作るのが難しい。そのため、劇団の数はあるのだけれど、特に若い人などは、大きな事を避けて、こぢんまりした中で自分たちの表現を探るしかない。観客も身内だけでまかなえてしまう。それは寂しい気がします。東京にはまだ仕事になるという幻想があるように思いますが、ここ大阪に残って演劇をやるには、社会で生きることと演劇とを両立させていかねばならない難しさがありますね。
――― 本日は、稽古前のお忙しい中、お時間をいただき大変ありがとうございました。
「百式サクセション」の公演を大変楽しみにしております。
聞き手: アーツサポート関西 事務局(大島、柳本) 取材日2016年10月6日