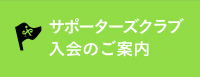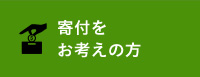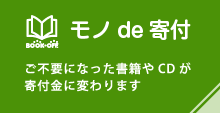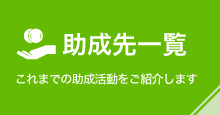【視察報告】7つの船2016実行委員会「7つの船」(美術)
2017年2月22日
H28年度 助成対象事業・視察報告
7つの船2016実行委員会「7つの船」
大阪の夜の水辺を船で航行しながら、船の内外に仕掛けられたさまざまなアート的な趣向を乗船者に体験させる取り組み。大阪を拠点に活動する現代美術アーティスト、梅田哲也らが中心となって企画したプロジェクトである。
「7つの船」とは、2016年12月の7日間に、大阪市街中心部の本町橋と住吉区の名村造船所跡地を往復する船を7往復させることに由来する。1日に本船(定員25名)と裏船(定員8名)の2艇が出航し、7日間にわたってそれぞれ上便・下便として1往復するため、出航数は全部で28便となる。定員はのべ450人以上におよび、定員制のアートイベントとしては小さくない規模である。
視察者の乗った便は本町橋出航の下り便であった。大阪市中心部の本町橋船着場から、東横堀川、道頓堀川を通過し、京セラドームを右に見ながら、大正区の工場地帯を抜けて住吉区の名村造船所跡地を目指す約2時間の航路である。船には本船・裏船とも屋根がなく、立ち上がれば頭が船体から出る格好となり、12月の夜の川面を渡る寒気が顔の皮膚に冷たくあたる。

出発に際して主催者の挨拶や航路の説明等は一切ない。参加者全員が乗船したのでいつのまにか岸を離れていた、という感じで、観客は、この時点でこれから何が起こるのか全く想定できない状態に置かれる。進行役をつとめる女性が、マイクで自分の心象風景的な言葉をぽつりぽつりと語りだすのみで、しだいに船内に非日常的な空気が漂い始める。
夜の水路を船で航行するだけでもすでに非日常的な体験なのだが、そこで提示される日常と非日常との境界が消失したような数々の奇妙な事象によって、参加者の意識が虚構と現実の狭間に囚われたような状況となる。高速道路の高架下を進む船の中から、梅田自身が懐中電灯を使って見上げるように橋の巨大な構造を浮かび上がらせたり、突然一艘の小型ボートが背後の暗闇から疾走してきて機関銃のようなものを乱射しながら追い抜かして行ったり、途中立寄った桟橋でトレンチコートを着た無言のサラリーマン風の男が乗り込んできたりといった、度合の強弱はあるものの、大阪の街の日常の中に無作為を装って配置された非日常性によって、ストーリーらしきものがその場に現れ、参加者の意識は水面の両側に連なる闇に閉ざされた夜の街・大阪の内部へと誘われていく。

芸術とは、作品を介して鑑賞者の意識を拡張させ新たな価値に触れさせるものであるならば、梅田は固定的な作品のかわりに、ナイトクルーズとそこに派生する様々な半日常的な事象からなる「状況」を創り出すことによって、鑑賞者たちの意識を解放し、見事なアート的な体験をもたらした。それには、あえて鑑賞者へのインストラクションを排除することで、未知の状況に向けられる彼らの自発的意識が高められていたことも寄与していたはずだ。これらを意図して作為と無作為の微妙な加減を差配しながらプロジェクトを構成した梅田の手腕は高く評価されよう。
「7つの船」では、梅田のほか、イギリスを拠点に映像作品を手掛けるさわひらきとベルリンを拠点に活動する現代美術アーティストの雨宮庸介の二人が加わり、この企画の構造に厚みを加えた。さわは、途中、移動する船の中からプロジェクターで川岸の建物に映像を照射したほか(視察者の回では残念ながら機器の不具合で実施されなかった)、終点の名村造船所跡地の船着場で対岸の倉庫の壁面に巨大な映像プロジェクションを行った。雨宮は期間中「裏船」に乗り込み、本船のクルーズに影響をおよぼずパフォーマンスを演出・実施していったほか、本プロジェクトと連動したSNSサイトにおいて、プロジェクトにまつわる歴史や事物などに触発されて書かれた詩情豊かなテキストを連載した。
しかし最も特筆すべきは、夜の水面の美しさであったかも知れない。漆黒の深みをたたえて静かに船を包み込む水面は、風がなければ鏡面のようになり、時折、岸辺の光を反射させながら、乗船した者の視覚に対して、これまで見たことのないような美しい世界の様相を提示して見せた。世界に対して最小限の作用を施し、その微妙な作為に気づかせることでアート的な意識の拡張をもたらす梅田のアプローチが今回対象としたのは、まさに大阪の街そのものであった。大阪という「場」・「空間」・「時間」を作品化した今回の取り組みは、アートの意味、その拡張性、また実際的な企画運営の観点から見て、極めて高い水準にある取り組みであったと考える。特にアートのひとつの表現方法として、新しい可能性を示すものであった。
ただ、無作為や偶然にゆだねられた部分が重要な役目を果たすとはいえ、一部、事象間のつなぎやそれが起こるタイミングにおいて改善の余地があったように見えた。プロジェクトの構成が極めて複雑に入り組み、舞台が水路を航行する船であるなど様々な制約を抱えたものであっただけに、さらに入念な準備が行われていたら作品の感動がより増していたのではないだろうか。
アーツサポート関西 事務局 大島 賛都

(Photo by :Yusuke Nishimitsu)